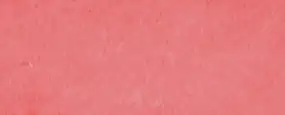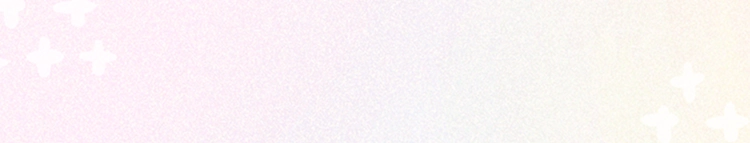本記事では、中絶手術に伴うリスクや合併症の内容と適切な対処法に加え、将来の妊娠への影響を防ぐための予防策についても解説します。
目次
中絶の安全性とリスクについて
中絶手術において重篤な合併症が発生する確率は1%未満であり、正期産での出産後と比べても、リスクは大幅に低いと言えます。
参考:MSD-人工妊娠中絶の合併症
ただし、すべての医療行為には一定のリスクが伴うため、事前に合併症の可能性や適切な対処法を知っておくことが大切です。
ここからは、中絶手術における主なリスク4つと、注意すべき合併症3つについて詳しく解説します。
中絶手術のリスク4つ
1.子宮内遺残
中絶手術後、胎盤や組織の一部が子宮内に残ることがあり、これを子宮内遺残と呼びます。
この遺残物が問題となるかどうかは、その量と質によって異なります。
症状
- 下腹部の痛みが続く
- 発熱や悪寒
対処法
異常を感じた場合は、できるだけ早めに医療機関を受診し、超音波検査などで状態を確認しましょう。
経過観察となる場合もありますが、必要に応じて追加の処置(子宮内容除去術)や薬の投与が行われることがあります。
遺残物を完全に取り除くためには、妊娠によって厚くなった子宮内膜の一部も掻き出す必要がありますが、過度な処置は子宮内腔の癒着を引き起こし、月経異常や不妊の原因となることがあります。
エコー検査で確認できないほどの少量であれば、数回の生理を繰り返すことで自然に排出され、hCGホルモンも徐々に消失していきます。
この方法は「生理的掻爬」とも呼ばれ、追加の処置をせずに経過を観察できる選択肢の一つです。
2.感染症
中絶手術後、細菌が子宮内に入り込むことで炎症が起こることがあります。
そのため、術後は予防目的で抗生剤の投与を行いますが、高熱を伴う強い腹痛がある場合は、子宮内感染や骨盤内感染の可能性があるため、早めの受診が必要です。
症状
- 発熱(38℃以上が続く)
- 下腹部の痛みや圧痛
- 悪臭のあるおりもの
対処法
感染症を防ぐために、術後にお渡しする抗生剤は、医師の指示通り最後まで服用してください。発熱や強い下腹部痛が続く場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
3.子宮穿孔(しきゅうせんこう)
子宮穿孔とは、手術中に器具が子宮の壁を貫通してしまうことを指します。
極めてまれな合併症ですが、子宮の壁が薄い方や、過去に子宮手術を受けたことがある方はリスクがわずかに高まることがあります。
症状
- 強い腹痛が突然起こる
- 大量出血(まれだが注意が必要)
- 血圧の低下やめまい(大量出血時)
対処法
術後に強い痛みや異常な出血が続く場合は、すぐに医療機関を受診してください。
4.出血
中絶手術後の出血は、子宮が回復する過程で自然に起こるものですが、その量や期間には個人差があります。
通常は1週間から10日程度続きますが、まれに1ヶ月近く続くこともあります。
また、ほとんど出血がない方や、おりもの程度の出血が続く方もいます。通常の範囲内の出血であれば問題ありませんが、異常な出血が続く場合は注意が必要です。
注意が必要な症状
- 生理の2日目くらいの多量の出血が3日以上続く
- 血の塊が大量に出る
- 貧血症状(めまい・ふらつき・顔色が悪い)を伴う
対処法
安静にしても出血が続く場合や、貧血症状がある場合は特に注意が必要です。術後の出血が通常よりも多いと感じたら、すぐに医療機関を受診してください。
中絶手術の合併症
中絶手術後の合併症は非常にまれとされていますが、万が一のリスクに備え、適切な対処法と早期の対応が術後の健康を守るために重要です。
1.子宮収縮不全(不良)
子宮収縮不全とは、中絶手術後に子宮が正常に収縮せず、妊娠前の状態に戻らない状態を指します。
子宮の収縮が不十分なため、出血が止まりにくく、長引くことがあります。
対処法
- 子宮収縮剤を使用し、収縮を促す
- 経過観察を行い、出血量が多い場合は追加の処置を検討
- 安静を心がけ、過度な運動を避ける
2.アッシャーマン症候群
アッシャーマン症候群とは、子宮の内側に傷ができ、子宮の壁同士がくっついてしまう状態を指します。
これにより、子宮内が狭くなったり、ふさがったりすることがあります。
主な原因として、流産や中絶手術の際に子宮内をかき出す処置(掻爬手術)、子宮内の感染症などが挙げられます。
異常を感じたら、早めに医療機関を受診することが重要です。
影響
- 生理不順や無月経が続く
- 将来的に不妊の原因になる可能性がある
診断と治療
診断には、子宮の状態を確認する「子宮鏡検査」や「子宮卵管造影」などの検査が使われます。
治療方法として、子宮の癒着を取り除くための手術(子宮鏡下手術)が行われることがあります。
術後に再び癒着が起こらないよう、子宮内に小さなバルーンを入れたり、ホルモン療法を併用することがあります。
3.中絶後遺症候群(PAS)
中絶手術後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)に似た症状が現れることを「中絶後遺症候群(PAS)」と呼びます。
感情が抑圧されることで、うつ症状や心身の不調が生じることがあり、精神的な負担が大きくなることもあります。
心のケアも術後の回復の大切な一部です。気持ちが不安定なときは、無理をせず、信頼できる人に話したり、必要に応じて医療機関や専門の相談窓口を利用しましょう。
症状例
- 気分が落ち込みやすい
- 怒りっぽくなる
- フラッシュバック(当時の記憶が突然よみがえる)
- 罪悪感や喪失感が続く
対処法
- 一人で抱え込まず、信頼できる人に話す
- 必要に応じてカウンセリングを受ける
- 時間をかけて気持ちを整理することが大切
中絶のリスクを最小限にするために
中絶手術におけるリスクをできる限り減らすために、以下のポイントを意識することが大切です。
信頼できる医療機関を選ぶ
中絶手術を受ける際は、適切な設備が整い、中絶の経験が豊富な医師がいる医療機関を選ぶことが大切です。
中絶手術の安全性やアフターケアの充実度は医療機関によって異なるため、事前に十分な情報を集め、安心して任せられる施設を選びましょう。
ひよりレディースクリニック福岡博多では、豊富な症例を持つ院長が中絶手術を担当し、術後のケアにも力を入れています。安心してご相談ください。
事前に十分な説明を受ける
中絶手術の流れやリスクを理解し、納得した上で中絶を選択することが大切です。
わからないことやご不安なことは、遠慮せず医師に相談しましょう。適切な情報を得ることで、術後の不安も軽減できます。
術後検診を受ける
中絶後の身体の回復を確認するため、術後検診を受けることが大切です。
なお、出血や痛みが長引くなど異常を感じた場合は、術後検診日を待たずに早めに受診しましょう。
将来の妊娠のために|Rh式血液型不適合妊娠の予防
Rh因子が「マイナス」の方は、中絶手術後に「Rh式血液型不適合妊娠」を予防することが大切です。
適切な対策をとることで、次の妊娠にリスクを残さず、安心して妊娠・出産を迎えることができます。
ここでは、Rh式血液型不適合妊娠の仕組みと予防策について詳しく解説します。
Rh式血液型不適合妊娠とは
血液型にはA・B・O・ABのほかに、「Rh因子(+ or -)」という分類があります。
母体がRhマイナスで胎児がRhプラスの場合、中絶時に胎児の血液が母体に入ることで、Rh抗体が作られることがあります。
なぜ予防が必要なのか?
Rh抗体が作られると、次の妊娠時に胎児の赤血球を異物とみなし、攻撃してしまう可能性があります。
初めての妊娠では、大きな影響はほとんどありません。
しかし、中絶・流産・分娩などで胎児の血液が母体に入ると、母体の免疫が「Rh(D)因子」に対する抗体を作り出してしまいます。
この抗体ができると、次回の妊娠時に胎児の赤血球が破壊され、胎児貧血や流産の原因となる可能性があります。
予防策|Rho(D)免疫グロブリンの注射
このリスクを防ぐために、抗D人免疫グロブリン製剤の注射を受けることが推奨されます。
この注射を受けることで、母体がRh抗体を作らないようにすることで、次回の妊娠に備えましょう。
将来の妊娠を守るために、Rhマイナスの方は医師に相談し、適切な処置を受けることが大切です。
ひよりレディースクリニック福岡博多では、抗D人免疫グロブリン製剤の注射を実施しています。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。