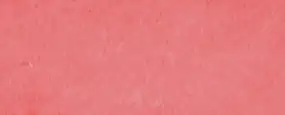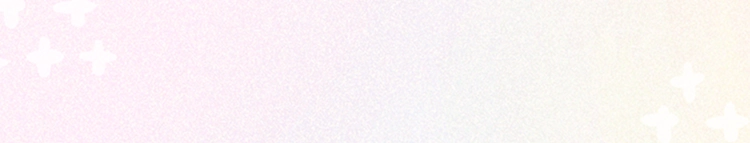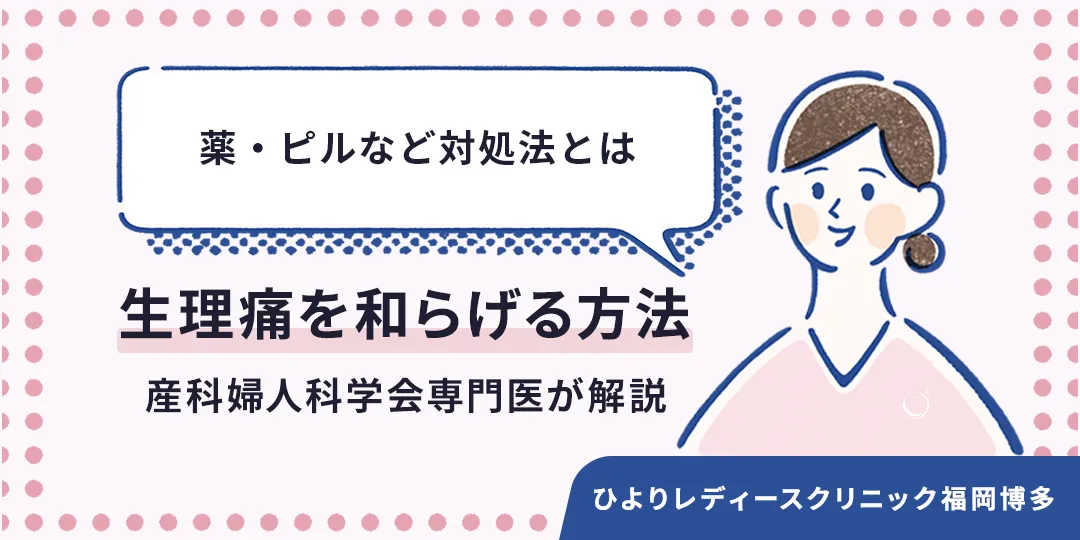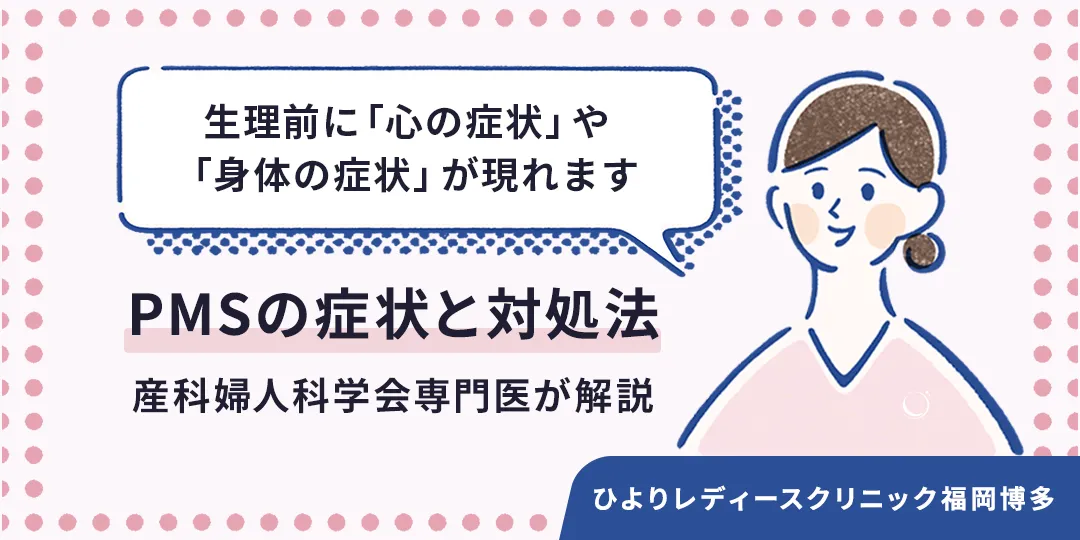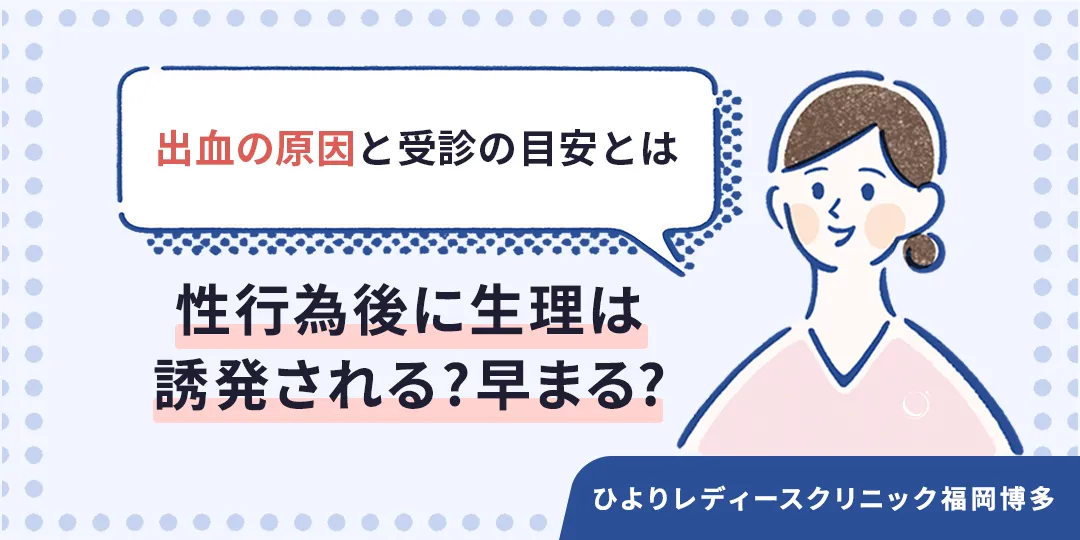ひよりレディースクリニック福岡博多は、生理のお悩みをご相談いただける婦人科です。
本記事では、生理の基本的な仕組みから、生理前・生理中の症状、そしてその対処法までをわかりやすく解説します。
目次
生理とは?
生理とは、女性の身体が妊娠の準備をするための自然な現象です。医学的には「月経」と呼ばれます。
生理は、体内のホルモンと深く関わっています。特に「エストロゲン」や「プロゲステロン」というホルモンが重要な役割を果たします。これらのホルモンの変動により、身体や感情にさまざまな変化が生じることがあります。
生理周期が乱れたり、生理前や生理中の症状が重い場合は、身体からのサインかもしれません。気になる症状が続く場合は、お早めの受診をおすすめします。
生理が起こる理由と仕組み
生理は、ホルモンの働きによって起こる、身体の自然な仕組みです。
脳からの指令により、卵巣から「卵胞刺激ホルモン(FSH)」と「黄体形成ホルモン(LH)」が分泌され、卵子の成熟が促されます。
生理(月経)終了後に、妊娠に備えて子宮内膜が厚くなり、受精卵を受け入れる準備が整います。しかし、妊娠が成立しなかった場合、ホルモンの分泌が減少し、不要になった子宮内膜が剥がれ落ちます。
この剥がれた子宮内膜が血液とともに体外へ排出されることを「生理」と呼びます。この一連の流れは、約一か月ごとに繰り返されるため、「生理周期」として知られています。
生理周期について
生理周期とは、生理の開始日から次の生理の開始日までの期間のことです。
一般的に、生理周期は21~35日程度が正常とされ、平均は約28日です。また、生理周期は、以下の4つのフェーズに分かれます。
卵胞期(生理開始~排卵前)
生理が始まると同時に卵胞期が始まります。卵巣内で卵胞が成長し、次の排卵に備える時期です。この期間にエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌が増加し、子宮内膜が再生されます。
排卵期(排卵のタイミング)
卵胞が成熟し、卵子が排卵される時期で、妊娠しやすい期間です。排卵直前には黄体形成ホルモン(LH)の分泌がピークに達し、卵巣が排卵を促します。
黄体期(排卵後~生理前)
排卵後、卵胞は黄体へと変化し、プロゲステロン(黄体ホルモン)を分泌して子宮内膜を厚くし、妊娠の準備を行います。
しかし、妊娠が成立しなかった場合、黄体は退縮し、ホルモン分泌が減少します。
生理期(生理の期間)
妊娠が成立しなかった場合、ホルモン分泌が低下し、不要になった子宮内膜が剥がれ落ち、血液とともに体外へ排出されます。これが生理です。
生理周期が規則的であることは健康の指標の一つですが、周期が不規則だったり、極端に短い・長い場合は、ホルモンバランスの乱れやストレスなどが影響している可能性があります。
以下で、生理前の症状・生理中の症状について、詳しく解説します。
生理前の代表的な症状4つ
生理前には、多くの女性が身体や感情の変化を経験します。
これらの症状は 「PMS(月経前症候群)」 と呼ばれ、頭痛・倦怠感・腹痛・情緒不安定などが代表的です。
症状の程度には個人差がありますが、日常生活に支障をきたすほど重い場合は「PMDD(月経前不快気分障害)」と診断されることもあります。
ここからは、生理前に起こりやすい4つの症状 について詳しく解説します。
PMS
PMS(月経前症候群)とは、生理前に起こる身体的および精神的な不調の総称です。症状は多岐にわたり、以下のようなものが代表的です。
- ☑身体的な症状:頭痛、乳房の痛み・ハリ、倦怠感、腹部の張り など
- ☑精神的な症状:イライラ、情緒不安定、憂うつ感、集中力の低下 など
PMSの症状は、通常、生理前3〜10日の間に現れ、生理が始まるとともに自然に改善します。
PMSの原因
PMSの原因は、ホルモンバランスの変化に関連しているとされていますが、ストレスや食生活、睡眠不足などのライフスタイルも影響を与えることがあります。
PMSについて詳しく知るPMDD
PMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも特に心の不安定さが顕著で、日常生活に大きな影響を及ぼす場合に診断される疾患です。
PMDDの症状には、強い不安感、抑うつ感、極度のイライラ、集中力の著しい低下、対人関係のトラブルなどが挙げられます。
これらの症状が原因で、仕事や日常生活に支障をきたすことが多く、場合によっては鬱病や不安障害と混同されることもあります。
PMDDの原因
PMDDの主な原因は、ホルモンバランスの変化とされていますが、脳内物質である「セロトニン」が深く関与しているとも考えられています。
PMDDの治療
PMDDの治療には、低用量ピルや抗うつ薬が使用されるほか、カウンセリングや認知行動療法(CBT)が効果的とされています。
また、ストレスの軽減や食生活の改善、規則正しい生活を心がけることも重要です。
「PMDDかも?」と感じた場合は、早めに婦人科で相談し、適切な診断と治療を受けることをおすすめします。
乳房の痛み・ハリ
生理前に乳房の痛みやハリを感じるのは、ホルモンの変動が原因です。
特にプロゲステロンの増加によって乳腺が刺激され、乳房が敏感になり、張りや痛みを感じることがあります。
症状には個人差があり、乳房全体が張る場合や、触れるだけで痛みを感じる場合もあります。
痛みを和らげる方法として、以下の対策が効果的です。
- 自分に合ったサイズのブラジャーを着用する
- 冷暖の調整をする
- マッサージや温めるケアを行う
ただし、片側の乳房だけに痛みがある場合や、症状が長引く場合は、乳腺症やその他の疾患の可能性もあるため、婦人科や乳腺科への受診をおすすめします。
身体の浮腫み
生理前に身体が浮腫むのは、ホルモンバランスの変化が原因です。
特にプロゲステロンの増加により、身体が水分を溜め込みやすくなるため、顔や手足が浮腫んでいる...と感じることがあります。また、血液やリンパの流れが滞ることも浮腫みの一因です。
浮腫みを軽減する方法として、以下の対策が効果的です。
- 塩分控えめの食事
- 適度な運動
- 足を高くして休む
- 温かいお風呂に浸かる
ただし、浮腫みが長期間続く場合や痛みを伴う場合は、腎臓や心臓の問題が隠れている可能性があるため、医療機関への相談を検討しましょう。
生理中の代表的な症状5つ
生理中には、腹痛や腰痛、倦怠感、頭痛など、さまざまな身体の不調を感じることがあります。
これらの症状は、「プロスタグランジン」と呼ばれる痛みを引き起こすホルモンの影響で生じることが多く、その程度には個人差があります。
また、症状が日常生活に支障をきたすほど重い場合は、子宮内膜症や子宮筋腫などの疾患が関係している可能性もあるため、一度婦人科で相談することをおすすめします。
生理痛がひどい
毎月の生理痛がつらいと感じる方は少なくありません。
生理痛は、子宮内膜を体外に排出する際に分泌される「プロスタグランジン」という物質が原因で起こります。この物質が多く分泌されると、子宮の収縮が強まり、痛みが増すことがあります。
「生理痛は薬を飲めばいい」と思われがちですが、ピルや適切な治療によって痛みを軽減できることをご存じでしょうか?
生理痛がつらいときは、無理に我慢せず、婦人科を受診することも選択肢の一つです。
生理痛がひどいときに病院へ行く目安
生理痛がひどい場合、子宮内膜症や子宮筋腫などの疾患が隠れていることもあります。
以下のような症状がある方は、早めに医療機関へ相談しましょう。
- 学校や仕事を休むほどの強い痛みがある
- 経血量が以前より増えた
- 生理が終わっても痛みが続く
- 生理以外のタイミングで出血がある(不正出血)
- 生理のたびに痛みが悪化している
- 性交時に痛みを感じる
生理痛を和らげるためには、市販の鎮痛剤だけでなく、ピルや漢方などの治療法もあります。
日常生活に支障をきたす生理痛は「月経困難症」と呼ばれ、適切な治療で症状を改善できる可能性があります。
出血量が多い|過多月経
生理中の出血量が多い場合、「過多月経」と呼ばれる状態の可能性があります。
過多月経の主な原因には、ホルモンバランスの乱れや子宮内膜症、子宮筋腫、子宮ポリープなどが挙げられます。
また、出血量が多いことで鉄欠乏性貧血のリスクが高まるため、早めの対応が重要です。
子宮頸管ポリープを詳しく知る過多月経の目安
以下のような症状がある場合は、医療機関での検査をおすすめします。
- ☑ナプキンを1時間以内に交換する状態が続く
- ☑塊状の血が頻繁に見られる
- ☑生理期間が8日以上続く
過多月経の治療法には、ホルモン療法や外科的治療などがあります。症状に応じて適切な治療を受けることで、日常生活の質を向上させることが可能です。
出血量が少ない|過少月経
出血量が極端に少ない場合、「過少月経」と呼ばれる状態の可能性があります。
過少月経の主な原因には、ホルモン分泌の低下やストレス、過度なダイエット、避妊薬の影響などが挙げられます。また、加齢に伴う卵巣機能の低下も要因の一つです。
出血量が少なくても、痛みや不快感がなければ問題ないこともありますが、以下のような場合には注意が必要です。
- ☑以前と比べて急に生理の量が減った
- ☑生理が極端に短くなった(2日以内で終わるなど)
- ☑不正出血や強い腹痛を伴う
このような症状がある場合は、医師に相談することで原因を特定し、適切な治療を受けることが可能です。
生理期間が長い
生理期間が8日以上続く場合、「過長月経」と呼ばれる状態の可能性があります。
過長月経の主な原因には、ホルモンバランスの乱れや子宮筋腫、子宮内膜症などの疾患が挙げられます。また、血液が止まりにくい体質や、服用中の薬の影響が関係していることもあります。
生理期間が長いと、身体への負担が大きくなり、貧血や疲労感を引き起こしやすくなります。以下のような症状がある場合は、医療機関での検査をおすすめします。
- ☑生理が8日以上続く
- ☑強い貧血症状(めまい・動悸・息切れなど)がある
治療法としては、ホルモン療法や薬物療法、場合によっては外科的治療が選択されることがあります。早めに対応することで、症状を軽減し、生活の質を向上させることができます。
生理期間が短い
生理期間が2日以下で終わる場合、「過短月経」と呼ばれることがあります。
この状態の主な原因には、ホルモン分泌の不足やストレス、加齢による卵巣機能の低下が挙げられます。また、避妊薬や一部の治療薬の影響で起こることもあります。
過短月経は、身体に大きな問題を引き起こさないこともありますが、他の症状(腹痛、不正出血など)を伴う場合は注意が必要です。
なお、生理が通常より極端に短い場合、「着床出血」の可能性も考えられます。その場合は、生理予定日から1週間後に妊娠検査薬を使用することをおすすめします。
生理が来ない...妊娠と病気の可能性
生理が来ない、または周期が不規則な状態は「生理不順」と呼ばれます。
通常、生理周期は25~38日程度が一般的ですが、生理の間隔が極端に短い・長い・不規則に変動する場合は、生理不順と考えられます。
生理不順の主な原因
生理不順は、さまざまな要因によって生じます。代表的な原因は以下の通りです。
- ホルモンバランスの乱れ
- ストレス
- 過剰な運動や栄養不足
- 体重の急激な変化
また、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や甲状腺疾患などの病気が関係していることもあります。
生理が来ない=妊娠の可能性も?
「生理不順だと思っていたら、実は妊娠していた」 というケースも少なくありません。妊娠の可能性がある場合は、生理予定日から1週間後に妊娠検査薬を使用して確認しましょう。
妊娠検査薬が陽性の場合
妊娠週数や正常妊娠の確認のため、お早めに婦人科を受診してください。
妊娠検査薬が陰性の場合
生理不順は一時的なものであることもありますが、長期間続く場合は注意が必要です。特に3か月以上生理がない場合や周期が大きく乱れる場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。
生理じゃないのに血が出る...不正出血
生理期間以外に出血がある場合、「不正出血(不正性器出血)」と呼ばれます。
不正出血の原因にはさまざまなものがあります。例えば、ホルモンバランスの乱れ、子宮頸管ポリープ、子宮筋腫、または子宮内膜炎などが挙げられます。
アフターピル(緊急避妊薬)の使用や、ストレス、過労も、不正出血を引き起こす可能性があります。
不正出血が少量で一時的なものであれば、特に心配がないこともあります。
しかし、出血が続く場合や、量が多い場合、または痛みを伴う場合は注意が必要です。これらの症状がある場合、重篤な疾患の兆候である可能性もあるため、お早めに婦人科を受診してください。
生理症状の治療にピルという選択肢
生理症状でお悩みの方には、低用量ピルやミニピルの使用が効果的な場合があります。
低用量ピルの特徴
低用量ピルは、ホルモンバランスを調整することで以下の症状を軽減します。
- 生理痛
- 過多月経(生理の量が多い状態)
- PMS(月経前症候群)
また、排卵を抑え、子宮内膜を薄く保つことで、生理の量を減らす効果も期待できます。
低用量ピルについて詳しく知るミニピルの特徴
ミニピルは、プロゲステロンのみを含むピルで、以下の特徴があります。
- 血栓症のリスクが少ない
- 低用量ピルを服用できない方にも使用可能
低用量ピルやミニピルは、避妊目的だけでなく、生理周期のコントロールや生理症状の改善を目的としても利用されています。
ミニピルについて詳しく知る生理症状にお悩みの方は婦人科へ
生理のお悩みは、身体や心に影響を与えることが多く、日常生活にも支障をきたす場合があります。しかし、正しい知識を持ち、適切なケアや治療を受けることで、多くの悩みを軽減することが可能です。
特に症状が重い場合や、不規則な生理に悩んでいる場合は、早めに医療機関を受診してください。医師へのご相談を通じて、ご自身に合った治療法を見つけることが大切です。
ひよりレディースクリニック福岡博多では、生理に関するご相談を承ります。
婦人科で生理に関するお悩みを軽減し、快適な毎日を送れる一助になれると幸いです。ぜひお気軽にご相談ください。
生理のよくあるご質問
生理が来ないのですが妊娠以外だと病気の可能性がありますか?
生理が来ない原因には、妊娠以外にもさまざまな要因が考えられます。ホルモンバランスの乱れやストレスの場合もあれば、病気が関与しているケースもあります。生理が来ない原因を知るためにも、まずは婦人科で検査をしてみてはいかがでしょうか。
産後の生理不順はどうしたらいいですか?
産後の生理不順は、ホルモンバランスの不安定さや授乳の影響、育児のストレスや疲労が原因となることが多いです。特に授乳中の場合、母乳分泌を促進する「プロラクチン」というホルモンが排卵を抑制する作用を持っているため、母乳育児を続けている方であれば、無排卵状態が続きます。断乳後に安定するケースがほとんどですが、生理の再開が大きく遅れる場合は、婦人科を受診することをおすすめします。
生理痛で病院に相談しても良いですか?
もちろんです。生理痛は多くの方がお悩みになる一方で、「鎮痛薬を飲めば大丈夫」と我慢されるケースが少なくありません。しかし、強い生理痛の裏に子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が隠れている場合もあります。早期に適切な診断と治療を受けることで症状の悪化を防ぐことができますので、どうぞお気軽にご相談にいらしてください。
生理周期とは何ですか?
生理周期とは、生理が始まった日から、次の生理が始まる前日までの期間を指します。一般的には25〜38日周期とされていますが、個人差があります。生理周期の中で、月経期・卵胞期・排卵期・黄体期の4つのホルモン変化が起こり、それぞれの時期に応じて身体の状態が変化します。生理周期を把握することで、排卵のタイミングや体調管理に役立てることができます。
生理前のイライラを抑える薬はありますか?
生理前のイライラ(PMS)を抑えるには、ピルや漢方の服用が有効です。低用量ピルは、ホルモンバランスを整えることでPMSの症状を緩和しやすくなります。また、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)や加味逍遙散(かみしょうようさん)などの漢方薬も、体質に合えばPMSの精神的な症状をやわらげる効果が期待できます。サプリメント(ビタミンB6、カルシウム、マグネシウム)も、補助的に取り入れるとよいでしょう。症状が強い場合や、日常生活に支障がある場合は、一度婦人科で相談することをおすすめします。
タンポンを入れると生理が早く終わるって本当ですか?
いいえ、タンポンを使用しても、生理の期間や経血量を短縮する効果はありません。ただし、ナプキンと違い、タンポンは経血を吸収するため、経血の量が可視化されにくくなることから、「生理が早く終わった」と感じることがあるかもしれません。実際には、生理は子宮内膜が剥がれ落ちる自然な生理現象であり、タンポンの使用によって生理の流れが変わるわけではありません。生理期間を短縮したい場合は、低用量ピルなどのホルモン療法が有効な場合もありますので、一度婦人科へご相談ください。